ECにおける決済方法の苦労した話
こんにちは。アプロ総研の受注担当です。
コラムって何を書いても良いそうなので、今回はネットショップにおける主な決済方法の注意事項と共に、実際にあった事例などを交え、苦労した話をすることにします。
こちらの記事で受注処理について「経験と要領の良さが求められる」と紹介されていますが、実際どういうこと?と想像が及ばないものです。が、決済の知識も幅広く必要になったりしてこれがまたややこしいのです。


その前に:オーソリの話。
ご存じの方は読み飛ばし推奨です。
クレジットカード決済に関するオーソリ(オーソリゼーション)について軽く説明しますね。
クレジットカード決済には「オーソリ」という重要なプロセスがあります。これは、カードを使ったお買い物が即座に口座から引き落とされるのではなく、実際の引き落としまでに時間がかかるために必要な仕組みです。また、クレジットカードには利用限度額が設定されています。
オーソリとは、簡単に言えば「そのカードが本当に使用可能かどうか」を確認するための審査です。具体的には、カードの有効期限が切れていないか、利用限度額を超えていないかなどをチェックします。例えば、月の利用限度額が10万円のクレジットカードで1万円の買い物をした場合、この1万円分が一時的に「利用可能枠」から差し引かれます。つまり、その月にさらに利用できる残額は9万円になります。この審査と手続きを「オーソリ」と呼びます。
もしオーソリが通らなければ、注文は成立しません。そのため、商品の発送前にオーソリが承認されない場合、注文がキャンセルされたり、別の支払い方法への変更を求められることがあります。これは、オーソリが通らないと販売者側が確実に代金を受け取れないからです。
なお、「後払い」についても同様に、信用情報(支払い能力)や本人確認のための「与信審査」が行われます。この審査に通らなければ、商品の発送はできません。
オーソリと与信審査は、クレジットカードや後払い決済の利用において、非常に重要なプロセスであり、これにより安全で確実な取引が保証されているんです。
クレジットカード
ECサイトの決済において、クレジットカードは最もスタンダードで、全体の約6割以上のシェアを占める主要な決済方法です。クレジットカードを利用することで、消費者は迅速かつ安全に商品を購入でき、販売者も即座に支払いを確認することができます。
オーソリ切れ
ECサイトでのクレジットカード決済において、「オーソリゼーション(オーソリ)」という重要なプロセスがあります。オーソリとは、カードの有効性や利用限度額を確認するための審査で、購入時に一時的に利用枠を確保する手続きです。オーソリが通らなければ、注文がキャンセルされたり、支払い方法の変更を求められたりします。
ECサイトにおける請求のタイミングは、大きく分けて二つのタイプがあります。一つは「購入完了時に請求を確定する」タイプ、もう一つは「発送時に請求を確定する」タイプです。後者のタイプが一般的ですが、どちらのケースでも購入時にオーソリを行い、確実に支払いが行われるように枠を確保します。
このオーソリによる枠の確保期間は、カード会社やカードの種類によって異なります。一般的には30日間の有効期間が設定されていますが、まれにもっと短い期間でオーソリが切れてしまう場合もあります。したがって、指定日配達を設定する際は、オーソリが切れるリスクを考慮し、30日以内の日付を選ぶことが推奨されます。
オーソリが切れていたことが発覚したら、お客様に連絡を取って銀行振り込みのお願いをしないといけないなど、その対応はかなり精神に来ます。 そしてこの原因はフロントの配達日指定の設定である事が多いです。
当然ですがバックオフィス業務はフロントの運用とつながっていますので、バックオフィス担当だからまるで無関係ということは無いのです。
オーソリの期間と指定日配達
オーソリの有効期間が切れてしまうと、確保していた利用枠が解除され、再度オーソリを取り直す必要が生じます。このため、指定日配達を希望する場合は、購入日から30日以内の日付を選択することが重要です。これにより、オーソリの切れによるトラブルを回避し、スムーズな取引を実現できます。
クレジットカード決済におけるオーソリは、消費者と販売者の双方にとって安全かつ確実な取引を支える重要な仕組みです。これを正しく理解し、適切に運用することで、ECサイトでの円滑な取引が可能となります。
キャンセルと返金の発生時期
通常のキャンセルの場合、オーソリが消去されるため、実際に引き落としが発生することはありません。しかし、問題となるのは、請求が確定した後に返金が発生する場合です。
請求確定後の返金処理
まず、締め日が過ぎていなければ、請求金額と返金金額が相殺されるため、引き落としが発生しません。この場合、消費者は返金を待つことなく、すぐに請求がキャンセルされるので、特に問題はありません。
しかし、締め日を過ぎている場合、状況は異なります。この場合、一度引き落としが行われ、返金は翌月に処理されることになります。具体的には、次月の引き落とし分から返金金額が相殺される形で実質的に返金が行われます。したがって、返金を希望するお客様には、このプロセスについて丁寧に説明することが重要です。
【返金時の注意点】
返金処理を行う際には、以下の点に注意する必要があります。
1.締め日を確認する: カード会社ごとに締め日が異なるため、返金処理のタイミングは個別に確認する必要があります。締め日を過ぎた場合、返金が翌月になる可能性が高いため、顧客に正確な情報を提供することが大切です。
2.顧客への案内: 返金処理が完了した旨を伝えるだけでなく、実際の返金がどのタイミングで行われるかについても詳しく説明します。返金のタイミングはカード会社によって異なるため、顧客にはカード会社に直接確認してもらうよう案内するのがおすすめです。
3.顧客対応の重要性: 返金処理に関する説明を怠ると、1~2ヶ月後に顧客からの問い合わせが発生し、対応に追われることになります。特に、返金が遅れることで顧客が困惑し、不満が生じる可能性があるため、初回の案内時にしっかりと説明することが求められます。
チャージバック(不正注文)
世間では転売行為は非難されがちですが、単なる転売、つまり自分で商品を購入し、それを高値で他の人に売る目的であれば、EC事業者にとってはまだ少し救いがあると言えるかもしれません。しかし、これとは別に、EC事業者にとって大きな問題となるのが、クレジットカードの不正利用によるチャージバックです。
チャージバックの仕組み
クレジットカードの所有者が不正利用に気付いた時点で、「これは私の買い物ではない」とカード会社に申請することができます。この申請が受理されると、カード会社は購入先のショップに対して「この注文はカードの不正利用だったので、お金を返してください」と連絡を送ります。このプロセスを「チャージバック」と呼びます。
ショップへの影響
チャージバックが発生すると、ショップは以下のような損害を被ることになります:
1.商品の損失: 商品はすでに発送されているため、ショップは商品を取り戻すことができません。
2.収益の損失: 支払いがキャンセルされるため、売上金を回収することができません。
3.時間とコストの損失: 不正注文に対応するための時間と労力がかかり、これに伴う運営コストも発生します。
このように、チャージバックの責任は基本的にショップ側にあり、ショップは一切の保証を受けられません。商品もお金も失い、さらに対応に時間を取られるため、まさに踏んだり蹴ったりの状態です。
不正注文の新たな手口
最近では、「盗んだカードがまだ有効かどうか」を確認するための不正注文が増えています。この手口では、商品を受け取る意図がない場合も多く、注文後に商品が返送されるケースもあります。しかし、商品が手元に返送されてきたとしても、チャージバックが成立しているため、ショップは一切の代金を受け取ることができません。つまり、商品のみが返ってくるものの、売上金は失われたままとなります。
【対策と注意点】
チャージバックによる損害を最小限に抑えるためには、以下の対策が重要です:
・不正利用検知システムの導入: 先進的な不正利用検知システムを導入し、疑わしい取引を事前に防ぐ。
・顧客確認の強化: 高額商品や不自然な注文には、追加の本人確認を行う。
・カード会社との連携: 不正利用が疑われる場合、迅速にカード会社と連携して対応する。
これらの対策を講じることで、チャージバックによる損害をある程度防ぐことができますが、完全にリスクを排除することは難しいため、常に警戒を怠らないことが求められます。
チャージバックの問題は、EC事業者にとって避けて通れない課題です。適切な対策を講じ、被害を最小限に抑えるための努力が不可欠です。
デビットカード
クレジットカード決済と似ているようで異なるデビットカードについて説明します。デビットカードは未成年でも作ることができ、お金の管理がしやすいなど、多くのメリットを持つカードです。しかし、クレジットカードと一見見分けがつかないにもかかわらず、異なる点があるため、返金や金額変更の際には注意が必要です。
返金までに時間がかかる
デビットカードの返金処理には、非常に時間がかかることがあります。「返金しました!」と通知しても、実際に返金が確認されるまでに1ヶ月以上かかることがあるため、顧客から「まだ返金されていません」という問い合わせを受けることがよくあります。クレジットカードと同様に、デビットカードの返金タイミングもカード会社ごとに異なるため、返金処理が完了した後も、実際の返金時期についてはカード会社に確認してもらうようお客様に案内するのが望ましいです。
さらに、デビットカードを使用する場合、返金までに最大で2ヶ月程度かかる可能性があることを事前に注釈として明示することも有効です。これにより、お客様の期待値を調整し、不要な不安や問い合わせを減らすことができます。
一時的な二重決済
デビットカードは即時引き落としが特徴です。このため、金額変更が発生した場合、変更分が再度引き落とされることで一時的に二重決済となることがあります。しかも、返金までの時間が長いため、二重決済の状態がしばらく続くことになります。
デビットカードかクレジットカードかを管理画面上で判別することは難しい場合が多いため、問い合わせを受けた際には、上記の点について詳細に説明する必要があります。一部の決済サービスでは、デビットカードの使用を制限するオプションが提供されているほど、この問題は認識されています。
事前の説明の重要性
デビットカードとクレジットカードの違いについては、管理画面からは一見見分けがつかないことも多いため、事前に詳細な説明を提供することが重要です。特に、返金や金額変更に関する注意点については、長くなってもきちんと説明するようにしましょう。これにより、顧客の理解を深め、後のトラブルを防ぐことができます。
デビットカードはその利便性から多くの人に利用されていますが、返金や金額変更の際には特有の問題が発生する可能性があります。返金に時間がかかる点や一時的な二重決済の問題について、事前にお客様に説明することで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。適切な説明と対応を心掛けることで、顧客満足度を高めることができます。
AmazonPay
でました~!ユーザーに1番人気の高いAmazonPayです。会員登録の手間が面倒だったり、複数のサイトにカード情報を登録したくなかったりするお客様にとって、AmazonPayは非常に便利な選択肢です。法人登録が必要なため、信頼性も高く、多くのユーザーに支持されています。
しかし、AmazonPayには他の決済方法にはない、いくつかの特殊な注意事項があるんです。
その1:オーソリが30日で切れる
AmazonPayのオーソリゼーション(オーソリ)期限は30日です。通常のお買い物では問題になりませんが、30日以上先の指定日配達を設定すると、オーソリが切れてしまい、商品代金の請求ができなくなる可能性があります。そのため、AmazonPayを導入しているショップでは、配達指定日を1ヶ月以内に設定することが推奨されます。営業日換算で指定する場合は、長期休暇などを考慮して、20営業日程度に設定するのが安全です。
さらに、30日以上先の日付を個別に依頼された場合には、日付が近くなってから再度注文してもらうように案内する必要があります。注文から発送までに1ヶ月以上かかることが多い受発注商品を扱うショップでは、AmazonPayの導入は避けた方が良いかもしれません。オーソリ切れが頻発すると、対応が非常に煩雑になります。
その2:金額変更の上限
AmazonPayには金額変更の上限が存在します。具体的には、購入金額の15%または8,400円のいずれか低い方です。例えば、4,000円の注文の場合、追加で請求できる金額は600円まで、60,000円の注文なら8,400円までとなります。「追加で商品をもう一つ」といったリクエストに対して変更を試みても、エラーが発生することがあります。
特に困るのは、離島への配送で送料を変更したい場合です。お客様の合意を得て変更しようとしても、エラーが発生して再注文をお願いする必要が出てくることがあります。この場合、事前に送料という商品をURLで共有し、同時に購入してもらうなどの工夫が必要です。ただし、金額変更の上限については、AmazonPayに相談すれば変更可能な場合もあるので、困った時は相談してみましょう。
その3:別人の住所に荷物が送られてしまう
AmazonPayでのもう一つの注意点は、誤って全く別人の住所を選択してしまうケースです。これは、ユーザーがAmazonのアドレス帳から誤った住所を選んでしまうことが原因です。荷物を受け取った本人がパニックになることもあります。
送り主が知人の名前であれば問題は少ないかもしれませんが、ショップの名前が出ていたり、配送先住所が購入者情報として表示される場合(例えばShopifyなど)では、混乱が大きくなります。これを防ぐためには、注文確認時に住所の再確認を促すメッセージを表示するなどの対策が考えられます。
AmazonPayは非常に便利で人気の高い決済方法ですが、オーソリの期限や金額変更の上限、配送先住所の選択ミスなど、いくつかの特殊な注意点があります。これらをしっかりと理解し、適切な対応を行うことで、スムーズな取引と顧客満足度の向上を実現できます。ショップ運営者はこれらの点に注意し、事前に顧客に対して適切な説明を行うことが求められます。
銀行振り込み

商材や顧客の年齢層によっては、銀行振り込みはまだまだ支持される決済方法ですよね。しかし、この銀行振込にはいくつかの注意点があります。
振り込み名義人が違う(注文との照合ができない)
時々、購入者と振り込み名義人が異なるケースがあります。例えば、購入者が担当者で、振り込み名義が会社名になっている場合です。このような場合、注文と振り込みを照合できず、本人確認が取れないことがあります。このような時には、電話やメールで購入者本人に確認を行う必要があります。ちなみに、楽天などのプラットフォームでは、このような情報を問い合わせることで振込確認をしてもらえることがあります。
銀行振り込み決済を選択していることに気づいていない
お客様が銀行振り込みを選択していることに気づかず、いつまでたっても振り込みがない場合があります。注文をキャンセルすると、「発送はいつですか」というお怒りのメールが届くことがありました。
意図せず希望とは異なる決済方法を選択してしまうこともあります。
このような場合、「あなたが銀行振り込みを選んだんでしょ?」という態度を見せるとお客様は気分を悪くします。「そちらが勝手に変更したんじゃないの?」と思われてしまうこともあるため、可能な限りデータやメールの履歴を確認し、「原因は分かりかねますが、そういう注文データで受け付けているため、発送処理ができなかった」と柔らかくお伝えしましょう。
微妙に振込金額が足りない
稀に、「商品代金のみを振り込み、送料を忘れていた」や「金額を誤認して間違えて振り込んでしまった」などのケースがあります。もちろん、金額が足りない場合は「追加で振り込んでください」とお願いするしかありませんが、500円の振り込みのために300円の手数料がかかるなどの状況で「じゃあキャンセルします」と言われるのではないかと心配になることもあります。
キャンセルの場合でも、振込手数料を差し引いての返金が基本ですので、非常に心が痛みます。もちろん、こちらの案内した金額に不備があればこの限りではありませんが…。
さらに、微妙に多く振り込まれていた場合もありました。この場合もお客様に伝えないわけにはいきませんが、振込手数料を差し引くとマイナスになってしまうという超レアケースに遭遇したこともあります。
1円多い1円少ないなんてこともある事なのでなかな悩ましい限りです。
銀行振り込みは非常に便利で支持される決済方法ですが、振り込み名義の不一致、決済方法の認識違い、微妙な金額不足など、注意すべきポイントがいくつもあります。これらの問題に対しては、丁寧で柔軟な対応が求められます。顧客とのコミュニケーションを大切にし、迅速に確認や対応を行うことで、スムーズな取引を心がけたいものですね。
代引き
出ました!!ECの運営側から最も嫌われているであろう代引きです!
代引き(代金引換)は、EC業界でしばしば運営者から避けられる決済方法として知られています。この方式では、商品を受け取る際に配送業者に代金を支払います。手数料は330円程度ですが、依然として根強い人気を誇っています。しかし、この方法には多くの課題が伴います。
返送になるケースが他の決済方法より多い
最近は代引きを廃止するショップもありますね。廃止の背景には転売問題も絡んできますが、代引きを導入しているショップからは度々「代引きをやめたい」という声が聞こえます。それはなぜか。
経理的な観点から入金元が1か所増え、その消込が必要になる点。送り状が異なり発行に手間がかかる点…等もありますが、実態はもっと深刻です。
実は、代引きは受け取り拒否になる可能性が他の決済方法より高く、また、送料分だけでも請求する方法がありません。
受け取り拒否など何らかの理由で商品が発送元へ返送となった場合、当然返送時にも送料が発生します。
更に生ものなど賞味期限が短ければ戻ってきた商品は廃棄せざるを得ません。廃棄にもコストがかかります。
クレジットカード決済であれば「返送となった場合も送料は返金しません」と最低限の損害を阻止できますが、代引きでは通常とは異なる方法で回収するしかありません。
勿論、代引きだろうと何だろうと購入者には支払いの義務がありますが、回収には手間もコストもかかり、ショップは泣き寝入りというのが実情です。
送料とはショップにとっては経費です。余分にかかれば一定の需要がある決済方法の代引きも廃止せざるを得ないというわけです。
不正注文のケースも
商品の購入と同時にメルカリなどのフリマサイトに、購入した商品が手元にないまま架空の出品を行います。
売れたらそのまま商品を受け取りますが、売れなかった場合受け取り拒否をするというパターンです。
な~~~~~にが在庫を抱える必要のないせどり!ドロップシッピング形式の賢い副業!じゃい!!!!
代引き廃止の動き
こうした背景から、最近では代引きを廃止するECショップも増えています。廃止の理由は多岐にわたりますが、主な要因は以下の通りです:
- 受け取り拒否のリスク:受け取り拒否による返送コストや廃棄コストが発生するため。
- 経理の負担:入金元が増えることによる消し込み作業の増加や、送り状発行の手間がかかるため。
- 不正注文の防止:転売目的の架空注文や、受け取り拒否による不正行為のリスクを減らすため。
代引きは、一見便利な決済方法ですが、ショップ側にとっては多くのリスクとコストを伴うため、廃止する動きが広がっています。購入者には支払いの義務がありますが、回収には手間とコストがかかるため、ショップが泣き寝入りするケースが多いのが実情です。ECショップにとって、送料は経費であり、余分なコストがかかる決済方法は避けざるを得ないという現実があります。
コンビニ決済
金額変更前の決済番号が有効である
決済代行会社のコンビニ決済で金額変更があった場合、金額変更前の振込番号が失効することはありません。変更したのに前の金額で振り込まれてしまうということもあり得ます。
(因みに楽天だと変更前の番号はすぐに失効します。これにより、顧客が誤った金額で振り込むリスクが減少します。こういうところは流石天下の楽天市場!と勝手に感謝しています。)
使用不可文字や文字数超過でエラーが起こる
例えば氏名が長すぎたり、記号が入っていたりすると決済エラーが起こる場合があります。電話番号の桁数がおかしい、等も原因としてあり得ます。
修正して再度審査依頼を掛けましょう。
(因みに楽天市場の場合、注文確認待ちステータスに留まり続ける為、個別に「注文確定」の処理をしてみましょう。どういう理由でエラーが出ているのか確かめることができます。)
後払い決済
請求書手数料は合算できない
2件の注文があった場合など、同梱して発送しているショップもあるかと思いますが、後払いの請求書をまとめることはできません。その為、請求書は2通発行され、手数料も2件分かかります。
もしも後払い決済の注文を同梱する場合は手数料分もまとめてしまわない様ご注意ください。
1件をキャンセルし、もう1件の金額を変更すれば、請求書は1通、手数料も1件分になりますが、後払いは与信調査に時間がかかるため手間がかかりますのでご注意ください。
キャンセルしても手数料は返金できない
後払いの手数料というのは、「請求書発行の手数料」という位置づけですので、請求書発行後のキャンセルだと手数料がなかったことにはなりません。
その為、ショップ責であるなら手数料を負担する必要があります。お客様都合でのキャンセルの場合も、手数料が返金されない理由をしっかりと説明することが重要です。
不正注文
後払いも不正注文で利用されやすい決済方法の一つです。
後払い決済は、不正注文に利用されやすい決済方法の一つです。以下のような手口があります:
- 受取先変更:出荷後に荷物の受取先を配送業者経由で変更し、請求書は元の住所に送られるため、支払いを逃れる。
- 荷受け代行や転送サービスの利用:荷受け代行や転送サービスを利用して、支払いを逃れる。
これらの不正行為からショップを守るため、後払い決済を導入する際には、保証制度のあるサービスを選ぶことが重要です。何が保証の対象となるのかを十分に確認し、リスクを最小限に抑えるようにしましょう。
後払い決済は便利な決済方法ですが、運営する側にはいくつかの注意点とリスク管理が求められます。複数の注文を同梱する際の請求書手数料の問題や、キャンセル時の手数料返金不可のルール、さらに不正注文のリスクに対する対策が必要です。保証制度のあるサービスを利用し、リスクをしっかりと管理することで、後払い決済を安全に運用することができます。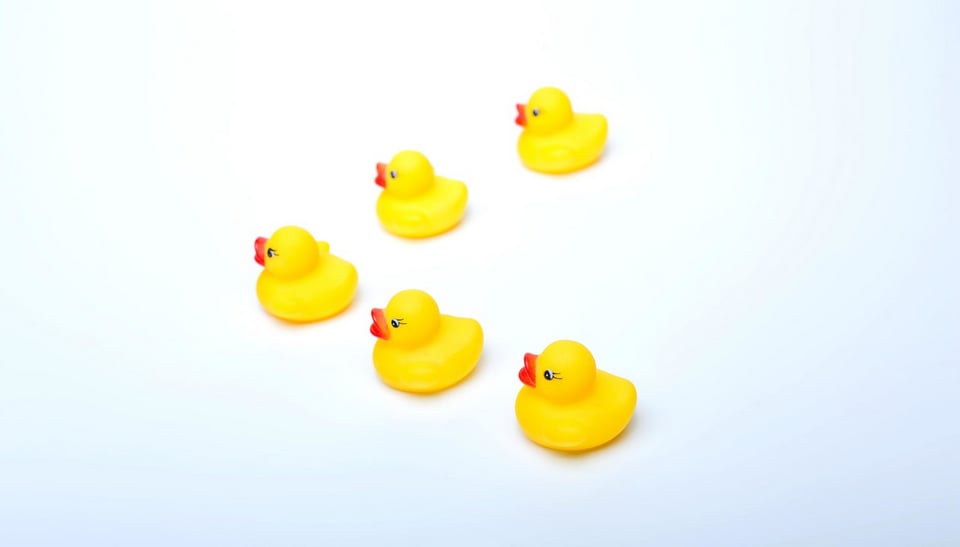
番外編 定期カートの場合
カード期限切れ・利用額超過
定期購入をしている場合、クレジットカードは登録されたものから毎月オーソリ→請求がされますので、うっかりカードの期限が切れていた、限度額を越してしまっていた!ということも…。
後払い決済の場合も引っ越しにより与信に通らなくなるなどがあります。
ご連絡して情報を更新してもらうか、別の決済方法に変更をお願いしなければいけません。
初回価格狙いの不正転売
これは、定期サービスの初回だけが異常に安いというビジネスモデルを狙った手口です。
回数縛りがないものは当然初回のみで解約ということもあるのですが、
転売しやすい商材などは、回数縛りがあったとしても狙われることがあります。プリペイドカードやデビットカードに現金をチャージしていなければいつまでたってもオーソリは通らず、実質逃げおおせることが可能な場合があります。
こうしてみると不正注文は本当に色んな手口がありますね。
不正注文の多様な手口
不正注文にはさまざまな手口があります。例えば、カードの期限切れや限度額超過による決済失敗、後払い決済での住所変更による与信調査不通過、そして初回価格を狙った不正転売などがあります。これらの手口に対応するためには、以下のような対策が必要です:
- 顧客情報の定期的な更新:クレジットカードの有効期限や利用限度額の確認を定期的に行い、必要に応じて顧客に情報の更新を依頼する。
- 厳格な与信管理:後払い決済の場合、引っ越しなどの際には新しい住所での与信調査を確実に行い、通過しない場合は別の決済方法を案内する。
- 不正転売対策:初回価格の設定に対しては、回数縛りを設けるとともに、プリペイドカードやデビットカードの利用を制限することを検討する。
これらの対策を講じることで、不正注文を減らし、健全な取引を促進することができます。ECショップ運営者は、顧客との信頼関係を維持しつつ、適切なリスク管理を行うことが求められます。
番外編2 利用限度額がある
例えばヤマト運輸の代金引換サービスの上限は30万円。
NP後払いの上限金額は55000円です。
このように、決済の金額によってはサービスによっては使えないことがあります。
逆に下限金額があり、クーポンやポイントを使い金額が0円になっているため注文ができない…なんてトラブルもあります。「注文ができない」とお問い合わせがあった場合、こういった可能性も疑ってみましょう。
トラブル対応のポイント
決済に関するトラブルが発生した場合、以下の点を確認することが重要です:
- 利用限度額の確認:顧客が選択した決済方法の利用限度額を確認し、上限を超えていないかチェックします。超えている場合は、別の決済方法を提案することが必要です。
- 下限金額の確認:注文ができない場合、クーポンやポイントの使用によって支払い金額が下限を下回っていないか確認します。下限を下回っている場合は、クーポンやポイントの利用を調整するように案内します。
- 顧客への説明:顧客に対して利用限度額や下限金額について丁寧に説明し、適切な対応を提案します。これにより、顧客の不満を減らし、スムーズな購入体験を提供できます。
決済サービスには利用限度額と下限金額が設定されている場合があり、注意することが重要です。高額商品を購入する際や、クーポンやポイントを使用する際には、利用限度額や下限金額に気を付ける必要があります。顧客から「注文ができない」といった問い合わせがあった場合、これらの点を確認し、適切な対応を行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ
受注処理はこういった決済に関する知識も必要になってきます。
日々、決済方法の特性や注意事項を理解したうえでそれぞれのケースに照らし合わせ、異なる判断・対応をしているんですね。店舗によってはもっと多様な決済方法があり、別の情報と組み合わせて対応が異なってきたりします。
誰にでもできそうで誰にでもできなかったり、属人化してしまう理由の一旦だったりします。
参考になれば幸いです。

フォローしませんか?

